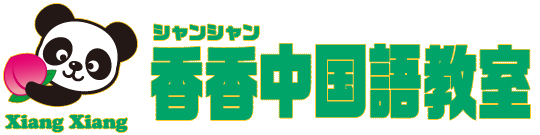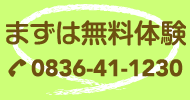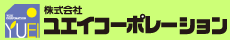Author Archive
- トップページ
 Archives
Archives
生徒さんの声 K・Hさんよりいただきました。
2012年 02月 20日
生徒さんの声 K・Hさん
①???あなたが中国語に興味を持ったきっかけを教えてください。
学生のころに、アルバイト先で中国の方と知り合い、中国語に興味を持ちました。当時は独学で始めて、その方との会話の中で思いついた単語を1つでも話すと喜ばれたので、それが楽しくて勉強していました。
②???どうして当教室を選ばれましたか?
宇部市にはなかなか中国語教室を見つけられなくて、少し遠方の教室に通っていましたが、会社からの帰宅途中で、たまたま目に止まったので、こちらの教室の門を叩いてみました。
③???感想
語学は少しずつでも毎日ふれる事が大事と言いますが、自分はやる気が出たり出なかったりとの繰り返しでなかなか上達できませんが、この教室に通う事で少しおっくうな時期でも中国語をがんばるぞと気持ちをリセットできています。また、一課終わるごとにテストがあるので一度勉強した内容を復習する事で、そこで本当に自分の身になってるなと実感しています。
(原文のまま掲載しております。)
チャイナドレス
2012年 02月 02日
こんにちは、今回はチャイナドレスの歴史についてご紹介します。
日本では、「チャイナドレス」としてすっかりお馴染みですが中国では旗袍と呼ばれています。
日本でよく知られているチャイナドレスは、実は1930年代に上海でモダンブームの影響を受けて改良された海派旗袍という上海式チャイナドレスなんです。タイトなデザインになったのもこの頃です。
当時、スカートとチャイナドレス風のブラウスなど中国と西洋が混ざり合った新しいファッションが生まれ、日本にも影響を与えました。
チャイナドレスのルーツは清の時代にまでさかのぼります。
当時、ヌルハチによって清王朝が興され、漢族は満州族の支配下に置かれました。
特に満州族は旗人という貴族に分類され、漢族との住み分けがはっきりとしていました。(北京では主に鼓楼大街に居住)
漢族は満州族の着ている服を「旗人の服」という意味で「旗袍」と呼んでいて、このころは長い裾のものが主流でした。
皇帝は満州族の支配に対する漢族の不満を解消するために、満州族にしか許されていなかったチャイナドレスの着用を漢族にも許し、婚礼衣装として一躍ブームになりました。
ちなみに、チャイナドレスの模様や色にもそれぞれ意味があります。
例えば、黄色は皇帝にしか着用が許されず、ウェディングドレスも赤色で花嫁は真っ赤なベールを被ります。
1956年におきた百花斉放という政治運動をきっかけに、それまでインテリ層の女性の間で普段着とし
て着用されていたチャイナドレスは中国大陸では廃れ、台湾や香港で独自の発展を遂げます。
現在、チャイナドレスを一着も持っていない人は珍しくなく、高級レストランや茶芸館で働いている人や伝統楽器の音楽家など一部の人しか着ません。
最近は、観光客向けにチャイナドレスのコスプレができる写真館もたくさんあるので中国旅行に行かれたさいはぜひ、試してみてはいかがでしょう?
中国人にとっての元旦と春節
2012年 01月 24日
こんにちは、今回は「中国人にとっての元旦と春節」についてお届けします。
日本では元旦を主にお祝いますが、中国では元旦と春節両方をお祝いします。
元旦は日本で言う1月1日、春節は旧正月で2月です。
この春節の時期は、人があまり行かないので航空券が安くなるといわれています。
中国人は元旦よりも春節を重んじます。
春節の夜は、家族みんなで「春節聯歓晩会」という日本で言う紅白歌合戦のようなものを観ます。
紅白と少し違うのは、オープニングで各56少数民族の歌や踊りのショーが催されることです。
お祝いムード一色の春節ですが、都市で出稼ぎをしている人のなかには里帰りによって生じる経済的・精神的な負担を嫌い、都市で過ごす人も年々増えてきています。
また、北京市内では普段花火とか爆竹は禁止されていますが、この日だけはOKです。
なので、街中では夜中の3時くらいまで爆竹の音が鳴り響きます。
春節の翌日には、?会という日本で言う縁日のようなところに行きます。
中国にもお年玉の習慣があり、相場は~200元くらいです。
春節の夜には華北では餃子を包み、華南では年夜飯というおせち料理を食べます。
この餃子の中には、アメや硬貨などを入れてその年の生活がどうなるか占います。
同じ春節なのに、北と南で習慣が違うのが外国みたいで面白いですね。
平安夜吃平安果(クリスマスイブに平安果を)
2011年 12月 26日
?こんにちは。クリスマス、どう過ごされましたか?
私は、家族でクリスマスケーキを食べました。
今回は、中国のクリスマスについてご紹介します。
中国では、クリスマスが近づくにつれて日本と同じようにイルミネーションが街中を彩り、クリスマスケーキが売りに出されます。
若者の間では、クリスマスパーティを開いたりもします。
欧米ではクリスマスの時には七面鳥の丸焼きを食べるとされていますが、中国では北京ダックを食べます。
そんな中国のクリスマスに欠かせない必須アイテムー平安果。
実は、この平安果はリンゴなんです。
中国では、クリスマス イブにこの平安果を贈りあうことによって来年の無病息災を祈ります。
なぜ、リンゴなのかー。
それは昔、ある街に住む学生が「平安」と「苹果」の音をかけて八百屋さんでリンゴを友人に贈ったことが始まりだと言われています。
みなさんも毎年、クリスマスにリンゴを親しい人に贈ってみてはいかがでしょうか?
きっと幸福な一年が訪れますよ。
中国のランチタイム
2011年 12月 17日
こんにちは!今回は、中国の人々のお昼ご飯・・・題して「中国のランチタイム」をお届けします。
中国人は脂っこいものを好む上に水と同じで冷たいご飯を好まないため、日本人のようにお弁当を持っていく習慣がありません。
それでも、上海など日本人や日系企業が多い都市ではコンビニで「便当」が売られています。
駅弁などもありますが、ご飯とおかず3品という非常にシンプルなものが多いです。
実は、南宋時代の「便當(=便利、好都合)」という言葉が日本の弁当の語源だといわれています。
この言葉が平安時代ごろに中国から日本に入り、なまって「べんとう」という言葉になったんですね。
では、中国人はお昼ご飯に何を食べるのか?
①学生・・・校内に学生食堂があり、値段も5元ほどでお腹いっぱい食べられます。メニューも。トマトと卵の炒め物など豊富!
大学によっては、イスラム教向けの食堂もあります。
支払方法は留学生は現金で支払いますが、現地学生は「給食カード」というカードで支払います。(セブンイレブンのnanaco方式)
ステンレス製プレートに、ご飯とおかずを3品位よそってもらいます。
大部分の学生は、1日3食全てをここで食べます。
中には、自分の学校より安い学生食堂がある学校を探してわざわざ食べに行くツワモノもいるとか。
②社会人・・・社内に社員食堂がある場合もありますが、街中の食堂も安くておいしいので街中の食堂で食べる人もいます。
③弁当を持っていく人・・・少数派ですが、ご飯とおかず一品だけというシンプルな弁当が多いです。
④漢民族以外の少数民族・・・その民族の料理を食べます。
このように、同じランチタイムでも弁当を持っていく人が多い日本とは違って中国では食堂で食べる人が多いという違いがあるのが面白いですね。